96 ’97 ’98 ’05 イエメン珈琲の旅
「琥珀の女王」と呼ばれ、世界の珈琲マニアに愛飲されている「イエメン・モカ」。私は`96,`97,`98,’05とイエメンに自ら訪れ、有名無名の産地をくまなく視察してまいりました。
その中でも、特に優秀な、バニー・イスマイリー(イブラヒム・モカ)、サイヒ(クラシック・モカ)、ヒラーラ(バニー・マタル)、三地方のコーヒー豆を取り扱うことに成功しました。これらのコーヒーは、今まではサウジ・アラビアだけに輸出されていて、現在、イエメンでは最も高く取引されているコーヒー豆です。
自然の恩恵をいっぱいに受け、無農薬、有機農法の手作りで作られる小粒に引き締まったこの豆は、本来、コーヒーがもっている味、香りをすべて有し、酸味、甘味、苦味、コク味、香味のバランスが秀逸で、世界最高級コーヒーの一つに数え上げられます。尚、イエメンの三大コーヒー商社の一つ「カブース社」の息子のイブラヒム・カブースさんより「イマーム」(信仰)のアラビアンネームをいただきました。
その中でも、特に優秀な、バニー・イスマイリー(イブラヒム・モカ)、サイヒ(クラシック・モカ)、ヒラーラ(バニー・マタル)、三地方のコーヒー豆を取り扱うことに成功しました。これらのコーヒーは、今まではサウジ・アラビアだけに輸出されていて、現在、イエメンでは最も高く取引されているコーヒー豆です。
自然の恩恵をいっぱいに受け、無農薬、有機農法の手作りで作られる小粒に引き締まったこの豆は、本来、コーヒーがもっている味、香りをすべて有し、酸味、甘味、苦味、コク味、香味のバランスが秀逸で、世界最高級コーヒーの一つに数え上げられます。尚、イエメンの三大コーヒー商社の一つ「カブース社」の息子のイブラヒム・カブースさんより「イマーム」(信仰)のアラビアンネームをいただきました。
イエメンモカについて
- (1)イブラヒム・モカ(中煎り)
- 苦味を少し抑え、モカ独特の甘味とスパイシーな香味が強く感じられるように焙煎しました。
- (2)イブラヒム・フレンチ(深煎り)
- 香ばしい苦味と、甘味を伴ったコクを大切にして焙煎しました。低めのお湯でじっくり抽出してください。
- (3)クラシック・モカ(中深煎り)
- 苦味とコクと甘味のバランスがほどよく、なめらかな味に焙煎しました。
- (4)ヤーフェ・ムニール・モカ(浅煎り)
- 旧北イエメンの優良産地、上ヤーフェで収穫される高品質なコーヒー。ライト・ミディアムにローストして、モカの持つさわやかな酸味と豊かな甘味を特徴にしました。
- (5)バニー・マタル(深煎り)
- 独特なモカ香と、やわらかな苦味を引き出すように焙煎しました。本来この地方の珈琲豆のことを、「モカ・マタリ」と呼ぶのです。イエメン最大のコーヒー産地。
「産地や焙煎濃度による味の違いをお楽しみ下さい。」
イエメン珈琲 PhotoAlbum
-
 マナハにある、ハジャラ村。イエメンでは山頂に家をつくる。
マナハにある、ハジャラ村。イエメンでは山頂に家をつくる。
-
 イブラヒム・モカを産出するバニー・イスマイルのコーヒー段々畑。
イブラヒム・モカを産出するバニー・イスマイルのコーヒー段々畑。
-
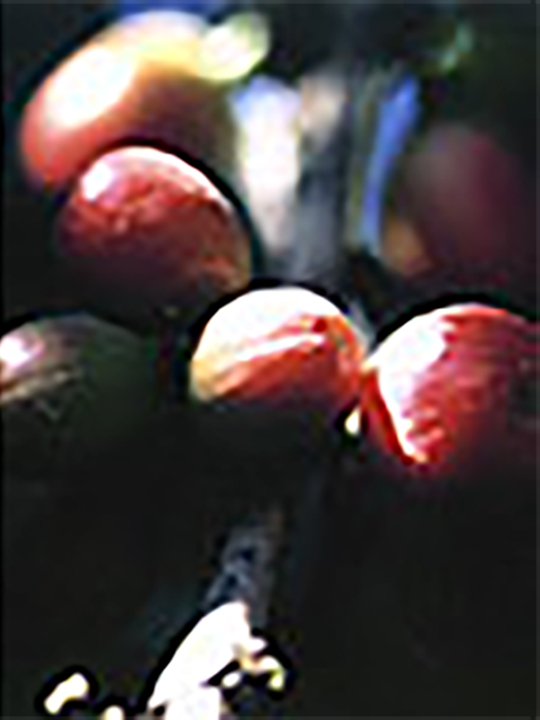 ナツメヤシの木に守られた、コーヒーの樹。イエメンでは、全てがナチュラルコーヒーです。
ナツメヤシの木に守られた、コーヒーの樹。イエメンでは、全てがナチュラルコーヒーです。
-
 各地でとれた、コーヒー豆の収荷所。マナハ。
各地でとれた、コーヒー豆の収荷所。マナハ。
-
 サナアの町の建物。
サナアの町の建物。
-
 脱穀は全て石臼で行われています。
脱穀は全て石臼で行われています。
-
 コーヒーの皮穀でつくられるイエメン独特のギシル・コーヒー。
コーヒーの皮穀でつくられるイエメン独特のギシル・コーヒー。
-
 紅海沿岸にあるモカの港町。18世紀までここよりヨーロッパにコーヒー豆が輸出されていたが、今は廃港になっています。
紅海沿岸にあるモカの港町。18世紀までここよりヨーロッパにコーヒー豆が輸出されていたが、今は廃港になっています。






